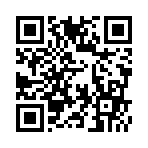スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2013年10月31日
“だいこん”のようす6
10月27日(日)に今シーズン2回目の播種をしました。
おなじみの1穴5粒点蒔きでございます。
本日は播種から5日目であります


見事に、同時発芽しました



若干、タネを蒔いた場所とは数cmズレている苗もありますが、生育には関係無いでしょう・・・。
大根は初めて栽培するので、気温と発芽や生育がどのように関係してくるのか未知であります。
ゆえに、10号鉢での栽培ですが、今回の発芽に関しては保温を気にしてみました。
不織布で鉢全体を3重に覆い、さらにその上へビニールをかけました。
可視透過率はかなり下がりますが、保温に関してはビニールハウス並に暖かいと思います。
それが功を制したかは分からぬが、発芽日数は9月下旬蒔きと同日数です。
とりあえずタネ袋には、この時期からの栽培は『トンネル栽培せよ』と書いてあるので、ある程度苗が大きくなるまでは、今後も保温して栽培していきます(#^.^#)
調度良い事に、寒い時期の育苗に便利な『ぽかぽかキャップ』と言う防寒資材があったので、それを暫らく使う事にしました。
9月下旬蒔きと10月下旬蒔きでは、どう生育に違いがあるのか?また、病害虫も含め、どんな影響があるのか?と言う部分を、実験的に検証したいと思う。
種はまだたくさんあるし、いろんな栽培パターンを勉強したいので、9月下旬蒔きが収穫し終わったら、今度は真冬の大根栽培に挑戦してみるつもりだ


おなじみの1穴5粒点蒔きでございます。
本日は播種から5日目であります



見事に、同時発芽しました



若干、タネを蒔いた場所とは数cmズレている苗もありますが、生育には関係無いでしょう・・・。
大根は初めて栽培するので、気温と発芽や生育がどのように関係してくるのか未知であります。
ゆえに、10号鉢での栽培ですが、今回の発芽に関しては保温を気にしてみました。
不織布で鉢全体を3重に覆い、さらにその上へビニールをかけました。
可視透過率はかなり下がりますが、保温に関してはビニールハウス並に暖かいと思います。
それが功を制したかは分からぬが、発芽日数は9月下旬蒔きと同日数です。
とりあえずタネ袋には、この時期からの栽培は『トンネル栽培せよ』と書いてあるので、ある程度苗が大きくなるまでは、今後も保温して栽培していきます(#^.^#)
調度良い事に、寒い時期の育苗に便利な『ぽかぽかキャップ』と言う防寒資材があったので、それを暫らく使う事にしました。
9月下旬蒔きと10月下旬蒔きでは、どう生育に違いがあるのか?また、病害虫も含め、どんな影響があるのか?と言う部分を、実験的に検証したいと思う。
種はまだたくさんあるし、いろんな栽培パターンを勉強したいので、9月下旬蒔きが収穫し終わったら、今度は真冬の大根栽培に挑戦してみるつもりだ



2013年10月27日
“だいこん”のようす5
9月27日(金)に“播種”した短大根『三太郎』!
本日で、播種より31日目となり、ちょうど1ヶ月経過しました(#^.^#)
白菜やキャベツ同様、葉が大きくなって防虫ネットにガツンガツンあたるようになってきた。
実際に、もう防虫ネットに引っかかり、葉が折れそうな苗もある。
ある意味、オレは大根の実よりも、葉の方が食いたい。大好物の『菜めし』でな!!!
作物が生長するのに大切な葉であるのは当然だが、人間のオレにとっても大切な“葉”って訳だ^m^
写真は、今までのその防虫ネットを外した場面だ!


地植えにしていれば、規格品のトンネル支柱で補えるであろうが、うちは土壌の問題で鉢栽培である。
鉢は地面に置き、規格品のトンネル支柱を地面に刺して固定しているため、どうしてもタッパが足りんくなるのだ・・・・・。
鉢の土に支柱を刺せば、タッパは足りるが、今度は空間面積が足りなくなり、要するに今度は横幅が足りなくなる。
防虫ネットも規格があるので、トンネルを高くすれば裾が足りなくなる。当然だよな!
この状況で、収穫時まで防虫ネットを外したくないので、これまたオリジナルで工夫するしかない訳だ。

とりあえずやってみた!下の写真は、出来上がりのモノである、、、、、
縦横の空間をかせぐ為に、トンネル支柱を『FRPダンポール』に変更し、さらに防虫ネットのサイズ調整の為、ネットをもう一枚付けたし二重にして、高さをかせいだ。
それにより、だいぶ高さをかせぐ事ができ、さらに鉢の位置を“千鳥植え”みたくズラして配置する事によって空間をうまく利用し、畝幅がとれない割にはゆったりと苗を配置する事ができた。
畝長には比較的ゆとりがあるので、かろうじてできたのである(*^^)v
短大根の葉が、どのぐらいの大きさまで生長するかは知らないが、この状態で収穫まで栽培するつもりだ。
防虫ネットが、なぜ二重なのか???ってのは、単純に資材コストをかけたくないので、家にあるものでまかなったからである。
規格サイズでは、いまいちフィットせ~へんし、規格外のサイズも注文すれば手に入るが、そこまでしたらただのバカだろっ・・・、、、、、だって大根1本1000円ぐらいになるしな!
やっぱ、採算が合わない栽培はアカンだろっwww
栽培技術はド素人で資材はオリジナル、それでもプロ同等以上の野菜を作ろうとしているんだから、つねにアイディアがいるのだ。
そもそも庭で栽培する時点で、規格外だけどな!
何にせよ、ただ実ればそれで良しでは無く、美しく芸術的で安全かつ美味い野菜を作ろうとしている訳だから、一筋縄ではイカン



さて、話あらため、、、、、
初め10苗分播種したのだが、先日、言う事を聞かん1苗を死刑にした・・・。
9苗となった訳だが、鉢が1個あまったので、本日あらためて播種しなおした。
いちおうタネ袋に記載されている播種時期は適期なのだが、10月中旬以降~翌3月までの播種は、、、
“トンネル栽培”と書かれている。
トンネルはわかるが、播種時から収穫までを寒冷紗かなんかで覆うって事か???
ビニールで覆った方が暖はとれそうなんだが、どうなんだろうか???
また、学ばなイカン事が増えてしまったな^_^;
播種適期は4月~9月、10月~翌3月、、、、、ってオイッ!年中O.Kじゃね~か
大根は連作関係ね~から、年柄年中栽培できるって事じゃん・・・って、今さらながら気付いたわ(#^.^#)
こりゃまた、オモローな事になってきたぜよ


本日で、播種より31日目となり、ちょうど1ヶ月経過しました(#^.^#)
白菜やキャベツ同様、葉が大きくなって防虫ネットにガツンガツンあたるようになってきた。
実際に、もう防虫ネットに引っかかり、葉が折れそうな苗もある。
ある意味、オレは大根の実よりも、葉の方が食いたい。大好物の『菜めし』でな!!!
作物が生長するのに大切な葉であるのは当然だが、人間のオレにとっても大切な“葉”って訳だ^m^
写真は、今までのその防虫ネットを外した場面だ!
地植えにしていれば、規格品のトンネル支柱で補えるであろうが、うちは土壌の問題で鉢栽培である。
鉢は地面に置き、規格品のトンネル支柱を地面に刺して固定しているため、どうしてもタッパが足りんくなるのだ・・・・・。
鉢の土に支柱を刺せば、タッパは足りるが、今度は空間面積が足りなくなり、要するに今度は横幅が足りなくなる。
防虫ネットも規格があるので、トンネルを高くすれば裾が足りなくなる。当然だよな!
この状況で、収穫時まで防虫ネットを外したくないので、これまたオリジナルで工夫するしかない訳だ。
とりあえずやってみた!下の写真は、出来上がりのモノである、、、、、
縦横の空間をかせぐ為に、トンネル支柱を『FRPダンポール』に変更し、さらに防虫ネットのサイズ調整の為、ネットをもう一枚付けたし二重にして、高さをかせいだ。
それにより、だいぶ高さをかせぐ事ができ、さらに鉢の位置を“千鳥植え”みたくズラして配置する事によって空間をうまく利用し、畝幅がとれない割にはゆったりと苗を配置する事ができた。
畝長には比較的ゆとりがあるので、かろうじてできたのである(*^^)v
短大根の葉が、どのぐらいの大きさまで生長するかは知らないが、この状態で収穫まで栽培するつもりだ。
防虫ネットが、なぜ二重なのか???ってのは、単純に資材コストをかけたくないので、家にあるものでまかなったからである。
規格サイズでは、いまいちフィットせ~へんし、規格外のサイズも注文すれば手に入るが、そこまでしたらただのバカだろっ・・・、、、、、だって大根1本1000円ぐらいになるしな!
やっぱ、採算が合わない栽培はアカンだろっwww
栽培技術はド素人で資材はオリジナル、それでもプロ同等以上の野菜を作ろうとしているんだから、つねにアイディアがいるのだ。
そもそも庭で栽培する時点で、規格外だけどな!
何にせよ、ただ実ればそれで良しでは無く、美しく芸術的で安全かつ美味い野菜を作ろうとしている訳だから、一筋縄ではイカン



さて、話あらため、、、、、
初め10苗分播種したのだが、先日、言う事を聞かん1苗を死刑にした・・・。
9苗となった訳だが、鉢が1個あまったので、本日あらためて播種しなおした。
いちおうタネ袋に記載されている播種時期は適期なのだが、10月中旬以降~翌3月までの播種は、、、
“トンネル栽培”と書かれている。
トンネルはわかるが、播種時から収穫までを寒冷紗かなんかで覆うって事か???
ビニールで覆った方が暖はとれそうなんだが、どうなんだろうか???
また、学ばなイカン事が増えてしまったな^_^;
播種適期は4月~9月、10月~翌3月、、、、、ってオイッ!年中O.Kじゃね~か

大根は連作関係ね~から、年柄年中栽培できるって事じゃん・・・って、今さらながら気付いたわ(#^.^#)
こりゃまた、オモローな事になってきたぜよ



2013年10月27日
“にんにく”のようす2
9月22日(日)に植えた、初栽培のにんにく(1種9鱗片)


本日までに、9鱗片中8鱗片が発芽しました


5鱗片が地植えで、4鱗片が鉢植えでございます。
10月20日(日)に一番最初に発芽した苗は、すでに11cmほどになり、エライ勢いで生長しています。


にんにくは、マルチシート栽培が基本かどうか知りませんが、草引きの手間や畝崩れ防止のため、地植えの方だけにマルチを張りました。
タネ植えの時にやれば作業も圧倒的に楽だったのだが、植えてしまってからマルチを張るのを思い出したので、芽が出揃うまで待っていた次第であります^_^;
こんな感じになりました、、、、、

発芽後のマルチ張りになってしまったので、穴の大きさや形が不恰好になってしまいました。
でもまあ、これで草も抜かんで良いし、大雨による畝崩れの心配も無くなりました。
あとは、適期に適量の追肥と、来年5月頃に摘蕾作業を行うだけで、後はほっといて収穫を待つだけです。特に、病害虫予防や対策も要りません!!!
なんて楽ちんな野菜なんでしょうかwww
株間を若干広くとっているので、大型のにんにくが無事収穫できるのか???・・・楽しみがまた一つ増えました





本日までに、9鱗片中8鱗片が発芽しました



5鱗片が地植えで、4鱗片が鉢植えでございます。
10月20日(日)に一番最初に発芽した苗は、すでに11cmほどになり、エライ勢いで生長しています。
にんにくは、マルチシート栽培が基本かどうか知りませんが、草引きの手間や畝崩れ防止のため、地植えの方だけにマルチを張りました。
タネ植えの時にやれば作業も圧倒的に楽だったのだが、植えてしまってからマルチを張るのを思い出したので、芽が出揃うまで待っていた次第であります^_^;
こんな感じになりました、、、、、
発芽後のマルチ張りになってしまったので、穴の大きさや形が不恰好になってしまいました。
でもまあ、これで草も抜かんで良いし、大雨による畝崩れの心配も無くなりました。
あとは、適期に適量の追肥と、来年5月頃に摘蕾作業を行うだけで、後はほっといて収穫を待つだけです。特に、病害虫予防や対策も要りません!!!
なんて楽ちんな野菜なんでしょうかwww
株間を若干広くとっているので、大型のにんにくが無事収穫できるのか???・・・楽しみがまた一つ増えました



2013年10月27日
“自生あけび”の収穫(*^^)v
昨年もほぼ同時期に収穫に至った“自生アケビ”!
鳥のフンや風にのって運ばれてきたであろう種。
なので、いつからそこにあるのか全くわからん程、年月も経っている木だ


しかし、長い年月は経っているものの、果実として収穫できたのは、昨年が初めてであった。
栽培しようと思って育てていないから、全て自然任せであり、なぜ、いきなし実が付いたのか?の要因も全くわからん



昨年、人生初めて“アケビ”を食ったオレだが、オレはあの食感も味も無理です・・・^_^;
とりあえず、うちのばあさんがアケビ好きなので、木は伐採せずそのままにしているのだが、近所のばあさん連中にも人気で、アケビを見に来たり、一緒に食ったりしている。
近所付き合いの良い潤滑果 (油)になっている“アケビ”である。
(油)になっている“アケビ”である。
住宅街の庭に自然に実る“アケビ”、、、、、めずらしいっち言やぁ~めずらしいかも知れんな



日の当たりや風通しなど、このアケビは良い位置に生えている。
オレとしては、庭の樹木は伐採して、ここにメロンの栽培ハウスを設置したいんだがなぁ~(-_-;)
巨峰栽培のタナもつくれそうだし・・・う~む。。。。。
鳥のフンや風にのって運ばれてきたであろう種。
なので、いつからそこにあるのか全くわからん程、年月も経っている木だ



しかし、長い年月は経っているものの、果実として収穫できたのは、昨年が初めてであった。
栽培しようと思って育てていないから、全て自然任せであり、なぜ、いきなし実が付いたのか?の要因も全くわからん



昨年、人生初めて“アケビ”を食ったオレだが、オレはあの食感も味も無理です・・・^_^;
とりあえず、うちのばあさんがアケビ好きなので、木は伐採せずそのままにしているのだが、近所のばあさん連中にも人気で、アケビを見に来たり、一緒に食ったりしている。
近所付き合いの良い潤滑果
 (油)になっている“アケビ”である。
(油)になっている“アケビ”である。住宅街の庭に自然に実る“アケビ”、、、、、めずらしいっち言やぁ~めずらしいかも知れんな



日の当たりや風通しなど、このアケビは良い位置に生えている。
オレとしては、庭の樹木は伐採して、ここにメロンの栽培ハウスを設置したいんだがなぁ~(-_-;)
巨峰栽培のタナもつくれそうだし・・・う~む。。。。。
2013年10月24日
“はくさい”のようす3
9月17日(火)~22日(日)の間に、4種8苗を地植え定植しました。
定植日より、本日で33~38日目になります!
10月21日(月)に、全苗3回目の追肥を液肥にて施しました。
つい1週間前にも記事にした白菜だが、かなり外葉が大きくなり、完全にトンネル防虫ネット内に収まりきらなくなってきた!
さらにまだまだどんどん大きくなっている気がする


・・・そこで、ネットにあたって葉に抵抗を与えてはイカンと思い、トンネル防虫ネットを外しました。
外したは良いが、それにより害虫に食害されては元も子もない!
オレは大の虫嫌いであり、見てくれも良くないと食う気が失せるのだ。
調度良い事に、今夏のメロン栽培跡地に白菜を植えている。
そこには、メロン用ハウスがそのまま組んであるので、それを利用する事にした。
今までも大雨の時は、ハウスのビニールを全閉し、雨風を凌いでいた。
今秋はやたらと雨が多いので、必要以上の水で苗が濡れると病気になってしまう(-_-;)
メロン栽培程では無いが、白菜と言えども水管理は侮れない。
マルチはしているが、特に“軟腐病”にかからぬ様に気を付けている。
さて、その肝心のハウスだが、、、、、※10月21日(月)晴天時日中撮影

 屋根はそのままビニール素材を使い、腰部分に防虫ネットを張り巡らしてみた
屋根はそのままビニール素材を使い、腰部分に防虫ネットを張り巡らしてみた


元々は、キャベツとレタス栽培に使っていた防虫ネットである。
レタスは既に全収穫済みだし、キャベツは意外に雨や害虫に強いから、トンネル内に収まりきらなくなったので撤収したのだ。
その防虫ネット、、、、、
上部分は支柱パッカーで止め、裾部分は自宅にあったアングルを置き、その重さで封鎖した。
完全無農薬栽培を成功させたいので、病害虫とも未然に防がなければならん・・・。
なので、降雨による自然の潅水は一切遮断して、全て管理した水分量だけを、適期に適度、適所に与えている。
ここも、オレのこだわり所だが、非常に労力がいる^_^;
特に、午後~翌日早朝までの潅水は一切厳禁である。だからいつ降るかわからん雨など言語道断だ!
うちの圃場での一番の白菜の天敵は『ナメクジ』である。
アブラムシでも無く、蛾の幼虫でも無く、このナメクジはトップクラスの害虫だ


昨年は、対処を何もしていなかったし、栽培要領も悪く、葉と葉の間にナメクジが入り込み、夜な夜な割り箸で1匹ずつ補殺していた。
全く追いつきません!なんつったて、栽培苗数10株ぐらいで、補殺は一晩で20匹を超えます。
それも毎晩毎晩、1ヶ月以上毎日・・・(T_T)
今シーズンは、栽培前に圃場全体に、ペレット状の駆除剤を撒いてあります。
圃場つったって庭なので、敷石やブロック塀周り、住宅壁沿い、倉庫の下などに撒き散らかしました。
1袋178円で100㎡の威力があると謳っている少々インチキ臭いこの粒々の駆除剤ですが、今シーズンは、今の所全くナメクジの被害はありません


潅水も徹底して管理しているので、両者の効果は大アリだと思います。
下の写真は、うちとブロック塀を挟んだ、すぐ裏のおばさん宅の白菜です。※本日、雨天夜間撮影


いるでしょ?やつらが・・・。


こんな白菜、食べる気失せるでしょ???
先日、裏のおばさんにナメクジ被害の相談を受けたんだけど、その時いろいろ話して「うん、わかった!」って言ってたのに・・・・・(-_-;)
完全にナメクジの“エサ化”してしまっているね。
中々、地面が乾きにくい住宅街の庭だから、何も対処しないとこうなっちゃうんです、ハイ・・・。
一方、“完全管理栽培型”のうちの白菜は?っと言うと、、、、、※本日、雨天夜間撮影

めちゃめちゃキレイでしょ???これ完全無農薬栽培ですよ(#^.^#)
はっきり言って、売れると思います。1玉500円以上でも買う人は買うでしょう!
味や食感はわかりませんが・・・・・^_^;
まあでも、言っっておくが、オレはオーガニック的な有機栽培や無農薬栽培には、、、、、、、、、、
全く興味が無い!!!
そもそも、そんな自然派志向な考えは、微塵の欠片も無い!!!
オレが興味あるのは、栽培技術のみ!
いかにして、糖度16度以上のメロンを作り、いかにして美しく芸術的でウマイ野菜を作るのか???
・・・っと言う事しか考えていない。
元々、オレにとっての野菜栽培は芸術作品を生み出す感覚だし、それが超高級品として扱われなければ(認められなければ)、栽培価値なんぞ全く無いのだ!
極論を言えば、野菜は畑で作るものでは無く、研究所や工場で作るモノである!
最近は、野菜=屋菜(やさい)って言葉も目につくようになった。
つまり、作物にとって“恵みの雨”なんぞある訳も無く、完全管理された施設栽培の方が、生産も安定するし美しく安全で、いつどこで誰が栽培しても遜色なく作れると思うのだ
現に、アールスメロンの産地である静岡の超有名ブランド『クラウンメロン』。
1玉数万円もするモノさえある。みんな食べたいと思うでしょ???
あれは、全部施設栽培だぞ。畑の土とは隔離して、専用の土を使っているしな。1滴の雨も必要ない。
何から何まで事細かく全部管理されている。
そして、生産者の研究開発努力と栽培技術は並じゃないよね!そな辺の1000円で食える露地モンとは苦労が違うわ。
まあ、庶民が食えるメロンを作るプロがいるから需要と供給が成立しているとも言えるがな!
、、、、、何にせよ、うちは素人の宅庭栽培である。
普通のサラリーマンだし、そこまで投資する資金も無ければ時間に制約もある・・・。
庭発信で、どこまでやれるのか???やっぱこれに尽きるな(^_^)v
白菜に関しては、一般的な株間より狭くして苗数を増やすしたため、球重はそこまで期待できないが、最低2.5kg~3kgは行ってほしいね(^^♪
まずは、そういう所からやってみているのだ・・・。
定植日より、本日で33~38日目になります!
10月21日(月)に、全苗3回目の追肥を液肥にて施しました。
つい1週間前にも記事にした白菜だが、かなり外葉が大きくなり、完全にトンネル防虫ネット内に収まりきらなくなってきた!
さらにまだまだどんどん大きくなっている気がする



・・・そこで、ネットにあたって葉に抵抗を与えてはイカンと思い、トンネル防虫ネットを外しました。
外したは良いが、それにより害虫に食害されては元も子もない!
オレは大の虫嫌いであり、見てくれも良くないと食う気が失せるのだ。
調度良い事に、今夏のメロン栽培跡地に白菜を植えている。
そこには、メロン用ハウスがそのまま組んであるので、それを利用する事にした。
今までも大雨の時は、ハウスのビニールを全閉し、雨風を凌いでいた。
今秋はやたらと雨が多いので、必要以上の水で苗が濡れると病気になってしまう(-_-;)
メロン栽培程では無いが、白菜と言えども水管理は侮れない。
マルチはしているが、特に“軟腐病”にかからぬ様に気を付けている。
さて、その肝心のハウスだが、、、、、※10月21日(月)晴天時日中撮影



元々は、キャベツとレタス栽培に使っていた防虫ネットである。
レタスは既に全収穫済みだし、キャベツは意外に雨や害虫に強いから、トンネル内に収まりきらなくなったので撤収したのだ。
その防虫ネット、、、、、
上部分は支柱パッカーで止め、裾部分は自宅にあったアングルを置き、その重さで封鎖した。
完全無農薬栽培を成功させたいので、病害虫とも未然に防がなければならん・・・。
なので、降雨による自然の潅水は一切遮断して、全て管理した水分量だけを、適期に適度、適所に与えている。
ここも、オレのこだわり所だが、非常に労力がいる^_^;
特に、午後~翌日早朝までの潅水は一切厳禁である。だからいつ降るかわからん雨など言語道断だ!
うちの圃場での一番の白菜の天敵は『ナメクジ』である。
アブラムシでも無く、蛾の幼虫でも無く、このナメクジはトップクラスの害虫だ



昨年は、対処を何もしていなかったし、栽培要領も悪く、葉と葉の間にナメクジが入り込み、夜な夜な割り箸で1匹ずつ補殺していた。
全く追いつきません!なんつったて、栽培苗数10株ぐらいで、補殺は一晩で20匹を超えます。
それも毎晩毎晩、1ヶ月以上毎日・・・(T_T)
今シーズンは、栽培前に圃場全体に、ペレット状の駆除剤を撒いてあります。
圃場つったって庭なので、敷石やブロック塀周り、住宅壁沿い、倉庫の下などに撒き散らかしました。
1袋178円で100㎡の威力があると謳っている少々インチキ臭いこの粒々の駆除剤ですが、今シーズンは、今の所全くナメクジの被害はありません



潅水も徹底して管理しているので、両者の効果は大アリだと思います。
下の写真は、うちとブロック塀を挟んだ、すぐ裏のおばさん宅の白菜です。※本日、雨天夜間撮影
いるでしょ?やつらが・・・。
こんな白菜、食べる気失せるでしょ???
先日、裏のおばさんにナメクジ被害の相談を受けたんだけど、その時いろいろ話して「うん、わかった!」って言ってたのに・・・・・(-_-;)
完全にナメクジの“エサ化”してしまっているね。
中々、地面が乾きにくい住宅街の庭だから、何も対処しないとこうなっちゃうんです、ハイ・・・。
一方、“完全管理栽培型”のうちの白菜は?っと言うと、、、、、※本日、雨天夜間撮影
めちゃめちゃキレイでしょ???これ完全無農薬栽培ですよ(#^.^#)
はっきり言って、売れると思います。1玉500円以上でも買う人は買うでしょう!
味や食感はわかりませんが・・・・・^_^;
まあでも、言っっておくが、オレはオーガニック的な有機栽培や無農薬栽培には、、、、、、、、、、
全く興味が無い!!!
そもそも、そんな自然派志向な考えは、微塵の欠片も無い!!!
オレが興味あるのは、栽培技術のみ!
いかにして、糖度16度以上のメロンを作り、いかにして美しく芸術的でウマイ野菜を作るのか???
・・・っと言う事しか考えていない。
元々、オレにとっての野菜栽培は芸術作品を生み出す感覚だし、それが超高級品として扱われなければ(認められなければ)、栽培価値なんぞ全く無いのだ!
極論を言えば、野菜は畑で作るものでは無く、研究所や工場で作るモノである!
最近は、野菜=屋菜(やさい)って言葉も目につくようになった。
つまり、作物にとって“恵みの雨”なんぞある訳も無く、完全管理された施設栽培の方が、生産も安定するし美しく安全で、いつどこで誰が栽培しても遜色なく作れると思うのだ

現に、アールスメロンの産地である静岡の超有名ブランド『クラウンメロン』。
1玉数万円もするモノさえある。みんな食べたいと思うでしょ???
あれは、全部施設栽培だぞ。畑の土とは隔離して、専用の土を使っているしな。1滴の雨も必要ない。
何から何まで事細かく全部管理されている。
そして、生産者の研究開発努力と栽培技術は並じゃないよね!そな辺の1000円で食える露地モンとは苦労が違うわ。
まあ、庶民が食えるメロンを作るプロがいるから需要と供給が成立しているとも言えるがな!
、、、、、何にせよ、うちは素人の宅庭栽培である。
普通のサラリーマンだし、そこまで投資する資金も無ければ時間に制約もある・・・。
庭発信で、どこまでやれるのか???やっぱこれに尽きるな(^_^)v
白菜に関しては、一般的な株間より狭くして苗数を増やすしたため、球重はそこまで期待できないが、最低2.5kg~3kgは行ってほしいね(^^♪
まずは、そういう所からやってみているのだ・・・。
2013年10月22日
“きゃべつ”のようす3
9月16日(月)に定植した2種13苗のキャベツ!
昨日、2回目の追肥を行った。液肥300倍10L(全苗分)。


本日は、定植日より37日目で、昨日のサニーレタスの記事にも書いたが、本来、、、、、、
キャベツのコンパニオンプランツとしてサニーレタスを実験目的で混植した。
・・・のはいいが、、、、、結果は全くわからず終わった(-_-;)
防虫ネットをしていたので、コンパニオンプランツによって害虫被害の軽減化が図れたかどうかよくわからん(-_-;)
また、混植する事によって、キャベツの生長促進作用の効果が得られるハズだったのだが、全てのキャベツの苗と混植したので、何も比較のしようが無い(-_-;)
しかし、昨年同時期に単品定植した同品種と比較すると、生長スピードはやや遅く、やや小型化している様な気もする(-_-;)気温や天候の影響もあるので何とも言えんかも知れんが・・・。

従って、実験はよくわからん結果に終わった。
だが、まさしくコレこそが答えなのかも知れんぞ!
要するに、コンパニオンプランツとは、科学的根拠がよくわからない栽培法であると言えるのではないか???
昔からよく言う『おばあちゃんの知恵袋』や、現代風に言うと『都市伝説』的な解釈だ。
プロ、素人問わず、どのウェブサイトを見ても、研究結果や実験結果は掲載されていない。
「OOと一緒に栽培すると良い」とは書かれているが、収穫した野菜の大きさや害虫被害の比較、その野菜成分の分析など、それがどんな結果をもたらしたのか???・・・までははっきりと明記されていない。
コンパニオンプランツが真実ならば、やはり、最低「OOからOO成分が分泌されてOOのホルモンの影響でOOとなり、OO染色体がOOになって遺伝子情報がOOとなり・・・etc、OOと言う結果になった!」ぐらいの、科学的説明と根拠は欲しいよなっ(-_-;)
お前ら責任もって明記しろよ


明記しないのはなぜだと思う?それは、都市伝説だからである、っとオレは思う。
苗屋は1本でも多くの苗を売りたいだろうし、ド素人はウェブ上で知った被りをしたいし、錯覚を真実と勘違い???・・・みたいな事で生まれた話しなんだろうと思うなオレは!
オレは二度とやんね~な

 別々に栽培するわっ!
別々に栽培するわっ!
まあ、無数にあるウェブ情報なので、オレが見落としているだけかもわからんがね(;一_一)
昨日、2回目の追肥を行った。液肥300倍10L(全苗分)。
左の写真が『みさき』、、、、、右の写真が『あまだま』、、、、、
本日は、定植日より37日目で、昨日のサニーレタスの記事にも書いたが、本来、、、、、、
キャベツのコンパニオンプランツとしてサニーレタスを実験目的で混植した。
・・・のはいいが、、、、、結果は全くわからず終わった(-_-;)
防虫ネットをしていたので、コンパニオンプランツによって害虫被害の軽減化が図れたかどうかよくわからん(-_-;)
また、混植する事によって、キャベツの生長促進作用の効果が得られるハズだったのだが、全てのキャベツの苗と混植したので、何も比較のしようが無い(-_-;)
しかし、昨年同時期に単品定植した同品種と比較すると、生長スピードはやや遅く、やや小型化している様な気もする(-_-;)気温や天候の影響もあるので何とも言えんかも知れんが・・・。
従って、実験はよくわからん結果に終わった。
だが、まさしくコレこそが答えなのかも知れんぞ!
要するに、コンパニオンプランツとは、科学的根拠がよくわからない栽培法であると言えるのではないか???
昔からよく言う『おばあちゃんの知恵袋』や、現代風に言うと『都市伝説』的な解釈だ。
プロ、素人問わず、どのウェブサイトを見ても、研究結果や実験結果は掲載されていない。
「OOと一緒に栽培すると良い」とは書かれているが、収穫した野菜の大きさや害虫被害の比較、その野菜成分の分析など、それがどんな結果をもたらしたのか???・・・までははっきりと明記されていない。
コンパニオンプランツが真実ならば、やはり、最低「OOからOO成分が分泌されてOOのホルモンの影響でOOとなり、OO染色体がOOになって遺伝子情報がOOとなり・・・etc、OOと言う結果になった!」ぐらいの、科学的説明と根拠は欲しいよなっ(-_-;)
お前ら責任もって明記しろよ



明記しないのはなぜだと思う?それは、都市伝説だからである、っとオレは思う。
苗屋は1本でも多くの苗を売りたいだろうし、ド素人はウェブ上で知った被りをしたいし、錯覚を真実と勘違い???・・・みたいな事で生まれた話しなんだろうと思うなオレは!
オレは二度とやんね~な


 別々に栽培するわっ!
別々に栽培するわっ!まあ、無数にあるウェブ情報なので、オレが見落としているだけかもわからんがね(;一_一)
2013年10月22日
にんにくのようす1“発芽!”
9月22日(日)に植えた、初栽培のにんにく(1種9鱗片)


今日で、まるっと1ヶ月である。その間これまで1度も記事にした事はなかった・・・。
そんな忘れ去れし“にんにく”であるが、一昨日の10月20日(日)、9鱗片中2鱗片が発芽し、本日さらに2鱗片が、地味~に発芽した。

現在まで9鱗片中4つ発芽した事になり、植え付けから初発芽まで実に29日間を要した


にんにくの発芽は、3~4週間かかるのが一般的らしいので、うちのは若干生長が遅れている。
深植えし過ぎと言う事も考えられるが、深さ6~7cmに芽の出るとがった方を上にして植えているので、そんなに間違ってもいないと思う。
今まで、土を乾かせた事は無く、水不足は考えられない。日当たりも悪くは無い位置にある。
何でもそうだが、生長が早いのは良いが、標準より遅いと失敗感が過るので、残り5鱗片もさっさと発芽してほしいわっ^_^;
発芽さえしれば、あとは来年の初夏までほぼ放ったらかしで良いので、手間はかからん作物である。
昨日の記事のサニーレタスに続き、これもコスパに優れており、ハイリターンであると言えるかな???

栽培労力はほとんど要らね~し、タネは国産品で12鱗片398円だった(B級品だけど・・・)ので、2個収穫できれば完全に元は取れると思う。
スーパーで売っている国産モノ(完成品)は、意外と高いからな


栽培期間が長いのがネックだが、まあそれも栽培の楽しみの一つとしておく事にする(^^♪



今日で、まるっと1ヶ月である。その間これまで1度も記事にした事はなかった・・・。
そんな忘れ去れし“にんにく”であるが、一昨日の10月20日(日)、9鱗片中2鱗片が発芽し、本日さらに2鱗片が、地味~に発芽した。
現在まで9鱗片中4つ発芽した事になり、植え付けから初発芽まで実に29日間を要した



にんにくの発芽は、3~4週間かかるのが一般的らしいので、うちのは若干生長が遅れている。
深植えし過ぎと言う事も考えられるが、深さ6~7cmに芽の出るとがった方を上にして植えているので、そんなに間違ってもいないと思う。
今まで、土を乾かせた事は無く、水不足は考えられない。日当たりも悪くは無い位置にある。
何でもそうだが、生長が早いのは良いが、標準より遅いと失敗感が過るので、残り5鱗片もさっさと発芽してほしいわっ^_^;
発芽さえしれば、あとは来年の初夏までほぼ放ったらかしで良いので、手間はかからん作物である。
昨日の記事のサニーレタスに続き、これもコスパに優れており、ハイリターンであると言えるかな???
栽培労力はほとんど要らね~し、タネは国産品で12鱗片398円だった(B級品だけど・・・)ので、2個収穫できれば完全に元は取れると思う。
スーパーで売っている国産モノ(完成品)は、意外と高いからな



栽培期間が長いのがネックだが、まあそれも栽培の楽しみの一つとしておく事にする(^^♪
2013年10月21日
にんじんのようす3“間引き1回目”
9月30日(月)に播種し、5日後の10月5日(土)に発芽し始めた“にんじん”


播種日当日を1日目とすると、本日は播種から22日目になります。
播種から約3週間経ち、そろそろ1回目の間引き時期じゃね???
・・・・・って事で、今はこんな感じに生長しています。
本日は、1回目の間引きを行いました(#^.^#)




以前、記事にも書いたが、この“にんじん”と“ホウレン草”、、、、、
双葉がどれなのか、よう分からんかったのだが、調べた結果、、、、、なるほど


草みたいなV型の細い葉が双葉だったのですね
つまり、現在本葉3枚目ぐらいの苗って訳です。
“にんじん”と“ホウレン草”、、、、、
双葉がマジそっくりなのだが、ひょっとして両者とも双葉までの遺伝子は一緒じゃね~の???
・・・ってか、にんじんは“セリ科”、ホウレン草は“アブラナ科”だよなぁ~
いったい、どうなってんだろ???




さて、人参の間引き方もさまざまな情報があるが、確か双葉が出そろう頃が1回目の間引き時期だったような気がするなぁ~・・・(;一_一)
まいっか
人参は間引くのを遅めにした方が良いと言う情報もあるし、ヒマな時に間引けばいいやっ(>_<)
そんな訳で、これでイイのだ~


-------------------------------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・10月21日(月)→播種から22日目
2回目の間引き・・・???
3回目の間引き・・・???
-------------------------------------------------------------------------------------------



播種日当日を1日目とすると、本日は播種から22日目になります。
播種から約3週間経ち、そろそろ1回目の間引き時期じゃね???
・・・・・って事で、今はこんな感じに生長しています。
本日は、1回目の間引きを行いました(#^.^#)
≪間引き前のようす≫、、、、、(before)

以前、記事にも書いたが、この“にんじん”と“ホウレン草”、、、、、
双葉がどれなのか、よう分からんかったのだが、調べた結果、、、、、なるほど



草みたいなV型の細い葉が双葉だったのですね

つまり、現在本葉3枚目ぐらいの苗って訳です。
“にんじん”と“ホウレン草”、、、、、
双葉がマジそっくりなのだが、ひょっとして両者とも双葉までの遺伝子は一緒じゃね~の???
・・・ってか、にんじんは“セリ科”、ホウレン草は“アブラナ科”だよなぁ~

いったい、どうなってんだろ???
≪間引き後のようす≫、、、、、(after)

さて、人参の間引き方もさまざまな情報があるが、確か双葉が出そろう頃が1回目の間引き時期だったような気がするなぁ~・・・(;一_一)
まいっか

人参は間引くのを遅めにした方が良いと言う情報もあるし、ヒマな時に間引けばいいやっ(>_<)
そんな訳で、これでイイのだ~



-------------------------------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・10月21日(月)→播種から22日目
2回目の間引き・・・???
3回目の間引き・・・???
-------------------------------------------------------------------------------------------
2013年10月21日
さにーれたす“最後の収穫!”
9月16日(月)に苗を定植したサニーレタス!
本日は、定植日より36日目です。
収穫時期真っ最中なのにも関わらず、なんと・・・
『花芽』が出来てしまいましたので、全部収穫しました。




こうして、初収穫から8日間で、早くもキャベツだけになりました・・・・。
従って、コンパニオンプランツとしての成果は、、、、、はっきり言ってわかりません(T_T)


キャベツの収穫まで、これより害虫との戦いが始まります


喰われてたまるか っつ~の(-"-)
っつ~の(-"-)
とりあえず、このサニーレタス栽培は大成功です


先日、近所のスーパーでサニーレタス(茎無しで葉のみのビニール袋詰め)を見かけましたが、収穫時より時間が経ちすぎているのか、ヨタヨタで新鮮さの微塵の欠片も無い商品が、158円で売られていました。
量も、うちのサニーレタス1苗分も無いくらいの枚数葉しか入っていませんでした。
こりゃ~家で栽培したサニーレタス食ったら、とてもスーパーのモンなんて食えんでしょうな(-_-;)
何回もこのブログで文字にしているが、このサニーレタスはノーリスク・ハイリターンな栽培野菜である。栽培労力は何も要らんし、苗だって58円の安さである。
種からならもっと安い!!!
超コストパフォーマンスに優れている栽培物だと思いますゼ!
ちなみに、今夏栽培したネットメロンのハウス栽培は、数万円以上のコストがかかっています^_^;
労力もハンパ無かったっす・・・・・。
来夏もメロンは栽培しますが、このサニーレタスも、もちろん栽培します(#^.^#)
サニーレタスさん・・・ありがとう


本日は、定植日より36日目です。
収穫時期真っ最中なのにも関わらず、なんと・・・

『花芽』が出来てしまいましたので、全部収穫しました。
こうして、初収穫から8日間で、早くもキャベツだけになりました・・・・。
従って、コンパニオンプランツとしての成果は、、、、、はっきり言ってわかりません(T_T)
キャベツの収穫まで、これより害虫との戦いが始まります



喰われてたまるか
 っつ~の(-"-)
っつ~の(-"-)とりあえず、このサニーレタス栽培は大成功です



先日、近所のスーパーでサニーレタス(茎無しで葉のみのビニール袋詰め)を見かけましたが、収穫時より時間が経ちすぎているのか、ヨタヨタで新鮮さの微塵の欠片も無い商品が、158円で売られていました。
量も、うちのサニーレタス1苗分も無いくらいの枚数葉しか入っていませんでした。
こりゃ~家で栽培したサニーレタス食ったら、とてもスーパーのモンなんて食えんでしょうな(-_-;)
何回もこのブログで文字にしているが、このサニーレタスはノーリスク・ハイリターンな栽培野菜である。栽培労力は何も要らんし、苗だって58円の安さである。
種からならもっと安い!!!
超コストパフォーマンスに優れている栽培物だと思いますゼ!
ちなみに、今夏栽培したネットメロンのハウス栽培は、数万円以上のコストがかかっています^_^;
労力もハンパ無かったっす・・・・・。
来夏もメロンは栽培しますが、このサニーレタスも、もちろん栽培します(#^.^#)
サニーレタスさん・・・ありがとう



2013年10月21日
だいこんのようす4“間引き3回目(最終間引き)”
9月27日(金)に播種した短大根『三太郎』


本日は、播種から25日目です。
播種から、もう約1ヶ月も経つのかいッ?
・・・・・ってな感じで、本日、最終間引きを行い、1穴1苗に絞りました。
7枚目の本葉がチョロッと育ち始めたぐらいなので、タイミング的にはちょっと遅い気もするが、まあこんなモンじゃないかねェ~???
ついでに、固形肥料を1苗10g追肥しました。
多分、多すぎるような気もしますが、まあ、エエですわ^_^;
≪間引き前のようす≫、、、、、(before)



≪間引き後のようす≫、、、、、(after)



-------------------------------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・10月6日(日)→播種から10日目
2回目の間引き・・・10月12日(土)→播種から16日目(1回目より6日後)、追肥:固形肥料1苗3g
3回目の間引き・・・10月21日(月)→播種から25日目(2回目より9日後)、追肥:固形肥料1苗10g
-------------------------------------------------------------------------------------------
間引いた苗は、けっこうボリュームもあったので、今回は“菜めし”にする事にしました。
・・・っと言っても、作るのはオレでは無いんだけどもね
いつも、栽培はオレ担当で調理は奥さん担当です。夫婦二人三脚ってやつですわwww



そんな訳で、これで最後の間引きも無事終わったのですが、、、、

だいぶ、葉が大きくなった事もあり、土寄せしても苗がすぐ倒れてしまう状況であります。
10苗栽培中の内9苗は、何とかバランスをとる事ができ、とりあえず良しとしましたが、1苗だけどうやっても言う事を聞かへんバカ苗がおりまして、気に食わないので死刑にしました。
さ・よ・う・な・ら・・・。
さて、収穫に至るまで、何苗生き延びる事が出来るんでしょうかね???



本日は、播種から25日目です。
播種から、もう約1ヶ月も経つのかいッ?
・・・・・ってな感じで、本日、最終間引きを行い、1穴1苗に絞りました。
7枚目の本葉がチョロッと育ち始めたぐらいなので、タイミング的にはちょっと遅い気もするが、まあこんなモンじゃないかねェ~???
ついでに、固形肥料を1苗10g追肥しました。
多分、多すぎるような気もしますが、まあ、エエですわ^_^;
≪間引き前のようす≫、、、、、(before)
≪間引き後のようす≫、、、、、(after)


-------------------------------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・10月6日(日)→播種から10日目
2回目の間引き・・・10月12日(土)→播種から16日目(1回目より6日後)、追肥:固形肥料1苗3g
3回目の間引き・・・10月21日(月)→播種から25日目(2回目より9日後)、追肥:固形肥料1苗10g
-------------------------------------------------------------------------------------------
間引いた苗は、けっこうボリュームもあったので、今回は“菜めし”にする事にしました。
・・・っと言っても、作るのはオレでは無いんだけどもね

いつも、栽培はオレ担当で調理は奥さん担当です。夫婦二人三脚ってやつですわwww
間引いた苗の根(実)は、すでに18cmを超えていました

そんな訳で、これで最後の間引きも無事終わったのですが、、、、
だいぶ、葉が大きくなった事もあり、土寄せしても苗がすぐ倒れてしまう状況であります。
10苗栽培中の内9苗は、何とかバランスをとる事ができ、とりあえず良しとしましたが、1苗だけどうやっても言う事を聞かへんバカ苗がおりまして、気に食わないので死刑にしました。
さ・よ・う・な・ら・・・。
さて、収穫に至るまで、何苗生き延びる事が出来るんでしょうかね???
2013年10月17日
“はくさい”のようす2
9月17日(火)~22日(日)の間に、4種8苗を地植え定植しました。
定植日より、本日で26~31日目になります!
全苗とも2回目の追肥をしました。
本日の白菜のようすです、、、、、(#^.^#)
かなり外葉が大きくなり、防虫ネット内に収まりきらなくなってきました!



前回1回目の追肥で、希釈率300倍と500倍、、、、、液肥の濃度を間違えると言う失敗をし、おかげで葉の先端がチリチリ枯れると言う濃度障害を起こしました(T_T)
まあ、軽度で済みましたが、商品としては、んんっ???ってなりますね



今回の液肥濃度も前回と同じ300倍の希釈率ですが、2週間程前とは気温が明らかに違います。
本日のこの地域、最低気温13℃、最高気温23℃でした。
平均気温が18℃と言う事や、太陽の南中高度も下がってきているので、直射日光も和らいで日中でも涼しく感じ、朝晩は寒いぐらいです。
これはもう、夏ではありませんね、、、、、、、
・・・って訳で、液肥メーカー規程の秋冬濃度(300倍)で10L散布しました。
効力があるまで数日かかるので何とも言えませんが、帰宅後の夜に確認した時は、特に問題ありませんでした。
このまま無事に一気に行ってくれっ(^_^)/
早く鍋モン食いて~


定植日より、本日で26~31日目になります!
全苗とも2回目の追肥をしました。
本日の白菜のようすです、、、、、(#^.^#)
かなり外葉が大きくなり、防虫ネット内に収まりきらなくなってきました!

中には、もうすぐ結球し始めるんじゃね?みたいな苗もあります。

前回1回目の追肥で、希釈率300倍と500倍、、、、、液肥の濃度を間違えると言う失敗をし、おかげで葉の先端がチリチリ枯れると言う濃度障害を起こしました(T_T)
まあ、軽度で済みましたが、商品としては、んんっ???ってなりますね



キャベツとレタスをまたいで見ると、こんな風景です。
今回の液肥濃度も前回と同じ300倍の希釈率ですが、2週間程前とは気温が明らかに違います。
本日のこの地域、最低気温13℃、最高気温23℃でした。
平均気温が18℃と言う事や、太陽の南中高度も下がってきているので、直射日光も和らいで日中でも涼しく感じ、朝晩は寒いぐらいです。
これはもう、夏ではありませんね、、、、、、、
・・・って訳で、液肥メーカー規程の秋冬濃度(300倍)で10L散布しました。
効力があるまで数日かかるので何とも言えませんが、帰宅後の夜に確認した時は、特に問題ありませんでした。
このまま無事に一気に行ってくれっ(^_^)/
早く鍋モン食いて~



2013年10月16日
“きゃべつ”のようす2
9月16日(月)に定植したキャベツ!
本日は、定植から31日目です。ちょうど1ヶ月ですね


昨夜未明に、この地域を通過した台風の影響も無く、すくすく育っています。
しかし、昨年栽培した同時期と比較すると、若干生長スピードが遅く感じられますが、気のせいかも知れません・・・。
さて、仕事から帰宅後のこと、、、、、
台風の強風にあおられ、折れている苗はないか?と、1苗ずつ点検していた時の事だ。
なんと!!!1枚の葉裏に、みた事ない虫がうじゃうじゃいました


見た感じ、今日生まれたて のような感じです。
のような感じです。
とりあえず、他の葉や苗に飛び火するとイカンので、その部分の葉をちぎり、室内で撮影しました。
虫の付いた葉をティッシュの上に乗せ、その辺を這いずり回られたら困るので、それごと、クッキーの入っていた空き缶(箱)に入れました。

おそらく、数100匹はいるでしょう・・・


こいつらが、うちの狭い圃場を這いずり回り、栽培中の野菜が虫だらけになる事を想像すると、、、、、
“オェ~!!!”っです(-_-;)
何の害虫かはまだ調べていませんが、多分、蛾の幼虫だと思われます。
コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウガ、はたまたウワバ系か???
後日、詳しく調べたいと思います。
上の写真のコントラストを、60%上げてみました。

黒いのは虫で、その虫の下側にある白いモノが卵だと思われます。余計気持ち悪くなりました(-_-;)
この害虫がいた葉の端っこに、白っぽい丸型のキズ痕みたいなモノもありました。
葉脈も無くなっており、裏表が透けて見えるくらいになっています。

この丸型のキズ痕と、害虫発生の因果関係は全くわかりませんが、害虫の種類も含め、後日調べます。
とりあえず、今の所この害虫どもは、1苗の1葉だけにしか繁殖していなかったので、他の苗は主だった被害は被っていません。
不幸中の幸いってやつでした・・・。
全く油断も隙も無いねェ~害虫って(;一_一)
本日は、定植から31日目です。ちょうど1ヶ月ですね



昨夜未明に、この地域を通過した台風の影響も無く、すくすく育っています。
しかし、昨年栽培した同時期と比較すると、若干生長スピードが遅く感じられますが、気のせいかも知れません・・・。
さて、仕事から帰宅後のこと、、、、、
台風の強風にあおられ、折れている苗はないか?と、1苗ずつ点検していた時の事だ。
なんと!!!1枚の葉裏に、みた事ない虫がうじゃうじゃいました



見た感じ、今日生まれたて
 のような感じです。
のような感じです。とりあえず、他の葉や苗に飛び火するとイカンので、その部分の葉をちぎり、室内で撮影しました。
虫の付いた葉をティッシュの上に乗せ、その辺を這いずり回られたら困るので、それごと、クッキーの入っていた空き缶(箱)に入れました。
おそらく、数100匹はいるでしょう・・・



こいつらが、うちの狭い圃場を這いずり回り、栽培中の野菜が虫だらけになる事を想像すると、、、、、
“オェ~!!!”っです(-_-;)
何の害虫かはまだ調べていませんが、多分、蛾の幼虫だと思われます。
コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウガ、はたまたウワバ系か???
後日、詳しく調べたいと思います。
上の写真のコントラストを、60%上げてみました。
黒いのは虫で、その虫の下側にある白いモノが卵だと思われます。余計気持ち悪くなりました(-_-;)
この害虫がいた葉の端っこに、白っぽい丸型のキズ痕みたいなモノもありました。
葉脈も無くなっており、裏表が透けて見えるくらいになっています。
この丸型のキズ痕と、害虫発生の因果関係は全くわかりませんが、害虫の種類も含め、後日調べます。
とりあえず、今の所この害虫どもは、1苗の1葉だけにしか繁殖していなかったので、他の苗は主だった被害は被っていません。
不幸中の幸いってやつでした・・・。
全く油断も隙も無いねェ~害虫って(;一_一)
2013年10月15日
ほうれん草のようす3“間引き1回目”
10月1日(火)に播種した“ほうれん草”


播種から2週間ほど経ちましたが、いつ間引けば良いのかイマイチ分かっておらず、何やら苗が込み合ってきましたので、間引く事にしました

 ・・・・・って、昨日の話しですけど^m^
・・・・・って、昨日の話しですけど^m^
今夜は台風の影響で、大雨です





あれさ~ 細いV型の葉が“双葉”なのかねェ
細いV型の葉が“双葉”なのかねェ
ほんで、その後にチョロッと育ってくる丸い葉が“本葉”なの
丸い葉の方を“双葉”だと思ってるんたが・・・。違うかっ(-o-;)
今まで見たことないモンでわからへんわ




このホウレン草の間引き方もいろいろありますね(#^.^#)
2回間引き、徐々に株間を広げて行くやり方と、1回である程度の株間を広げたあとは、収穫までそのまま、・・・っと言うやり方。
畑やプランターなどの栽培条件によっても違うみたいですね。
要は、株間を広げれば、1苗が大きく育つものの面積当たりの苗数は減り、株間を狭くとれば、苗数は稼げるが苗は小型化する・・・ってな訳だ
この株間のとり方は、どんな野菜の苗にも共通して言える事ですね。

オレは欲張りだから、株間をそれ程広げずに、小型でもたくさん収穫できる方を選択した!
すなわち、それぞれの株間を3cm~6cm程(まちまち)にして、収穫まで今回の1回だけの間引きで済ませる事にしたのだ。間引く回数が減れば、それだけ作業効率もアップするからね


間引き後、時期的にまだ早いかもかもですが、化成肥料を“パラッ”っと蒔いておきました。
もうこれで栽培はほとんど終わりで、あとは収穫まで適当に水をやっておけば良い(*^^)v
元々、狭い庭で苗数=収量をどれだけ稼ぐか???に重きを置いて栽培しているので、他の野菜も密植傾向にあるしな^_^;
・・・っと言う訳で、このまま収穫まで行きますよん


・・・・・っと、、、、、そうそう、、、、、
今日は台風対策でこのクソどしゃぶりの中、雨風から苗を守るために、育苗中の大根、ニンジン、ホウレン草の苗にビニールをかけました








不織布や防虫ネットの上からのビニール掛けなので、風の通りが悪いから苗がフニャ~ってならんか心配である





播種から2週間ほど経ちましたが、いつ間引けば良いのかイマイチ分かっておらず、何やら苗が込み合ってきましたので、間引く事にしました


 ・・・・・って、昨日の話しですけど^m^
・・・・・って、昨日の話しですけど^m^今夜は台風の影響で、大雨です





これは昨日撮影した間引き後の写真です、、、、、
あれさ~
 細いV型の葉が“双葉”なのかねェ
細いV型の葉が“双葉”なのかねェ
ほんで、その後にチョロッと育ってくる丸い葉が“本葉”なの

丸い葉の方を“双葉”だと思ってるんたが・・・。違うかっ(-o-;)
今まで見たことないモンでわからへんわ



このホウレン草の間引き方もいろいろありますね(#^.^#)
2回間引き、徐々に株間を広げて行くやり方と、1回である程度の株間を広げたあとは、収穫までそのまま、・・・っと言うやり方。
畑やプランターなどの栽培条件によっても違うみたいですね。
要は、株間を広げれば、1苗が大きく育つものの面積当たりの苗数は減り、株間を狭くとれば、苗数は稼げるが苗は小型化する・・・ってな訳だ

この株間のとり方は、どんな野菜の苗にも共通して言える事ですね。
オレは欲張りだから、株間をそれ程広げずに、小型でもたくさん収穫できる方を選択した!
すなわち、それぞれの株間を3cm~6cm程(まちまち)にして、収穫まで今回の1回だけの間引きで済ませる事にしたのだ。間引く回数が減れば、それだけ作業効率もアップするからね



間引き後、時期的にまだ早いかもかもですが、化成肥料を“パラッ”っと蒔いておきました。
もうこれで栽培はほとんど終わりで、あとは収穫まで適当に水をやっておけば良い(*^^)v
元々、狭い庭で苗数=収量をどれだけ稼ぐか???に重きを置いて栽培しているので、他の野菜も密植傾向にあるしな^_^;
・・・っと言う訳で、このまま収穫まで行きますよん



・・・・・っと、、、、、そうそう、、、、、
今日は台風対策でこのクソどしゃぶりの中、雨風から苗を守るために、育苗中の大根、ニンジン、ホウレン草の苗にビニールをかけました









不織布や防虫ネットの上からのビニール掛けなので、風の通りが悪いから苗がフニャ~ってならんか心配である



2013年10月14日
“さにーれたす”のようす2
サニーレタスは、昨日記事(この時の写真は3日前に撮影)にしたばっかだが、たった数日で、、、、、なんと ・・・赤みを帯びてきたので、記録しておく(^_^)/
・・・赤みを帯びてきたので、記録しておく(^_^)/

前に記事にしたが、赤色種のサニーレタスが、なぜ赤くならず緑色のままなのか???
理由は3つあった・・・。覚えているかなぁ~^_^;
忘れてしまった人は、、、、、
10月10日(木)記事『“さにーれたす”のようす1』を読んでくださいな


(↑ ↑ ↑ 赤文字部分をクリック ↑ ↑ ↑すると、記事にリンクするよん。)

そうっ!その理由の一つに、気温が高いと赤くならない・・・、ってのがあったよね?
今日は、それをこの目で確かめれたので、またまた記事にしてみた(*^^)v
たぶん、初めて栽培する人は、オレと同じ疑問をもつと思うからさっ!
ここ数日、朝晩グッと冷え込みまして、この地域の最低気温は14℃~16℃、最高気温は24℃~26℃となっており、一日の平均気温が20℃となった。
サニーレタスは、平均気温が20℃頃にならないと、色素成分の“アントシアン”が分解されず、
赤発色しないそうだ!!!

知識はあっても、自分の目で実際に確かめないと、こう言うのって中々納得できないでしょっ!
赤くならない理由は、他にも二つあるからね。
潅水過多と窒素過多・・・、そして今回の気温の問題。
答えがわかってしまえば、“ふ~ん”ってなるけど、それまでは、その答えを見つける為にあれやこれやと考えたりするもんだしね(#^.^#)
今回の場合、うちのサニーレタスがなぜ赤くならなかったのか???は、、、、、
ズバリ!・・・気温が高かったからでしょう(丸尾君風)
4日前に記事にした時の写真と見比べると、色の違いがはっきりわかります!!!


・・・こうして、一つの疑問が解消された。
やっぱこう言う一つ一つの小ちゃな事が、栽培のおもしろさにつながるんだなぁ・・・コレがまた(^^♪
今夏のメイン栽培でもあった、“メロン”!
こいつは、こう言う小ちゃな疑問や問題が他の野菜以上に細かくたくさんあってね、それを一つ一つ検証して工夫して解決して行く事によって、より質の高い果実が作れる事につながるんだ


メロン初栽培で、菜園歴1年半のオレが、何の設備も無い宅庭でも糖度15度以上のメロンが収穫できたのは、それらを積み重ねたからなんだなぁ・・・


マジ野菜栽培は奥ふけ~な~(>_<)
あっ!テレビ見てくれた???
 ・・・赤みを帯びてきたので、記録しておく(^_^)/
・・・赤みを帯びてきたので、記録しておく(^_^)/前に記事にしたが、赤色種のサニーレタスが、なぜ赤くならず緑色のままなのか???
理由は3つあった・・・。覚えているかなぁ~^_^;
忘れてしまった人は、、、、、
10月10日(木)記事『“さにーれたす”のようす1』を読んでくださいな



(↑ ↑ ↑ 赤文字部分をクリック ↑ ↑ ↑すると、記事にリンクするよん。)
そうっ!その理由の一つに、気温が高いと赤くならない・・・、ってのがあったよね?
今日は、それをこの目で確かめれたので、またまた記事にしてみた(*^^)v
たぶん、初めて栽培する人は、オレと同じ疑問をもつと思うからさっ!
ここ数日、朝晩グッと冷え込みまして、この地域の最低気温は14℃~16℃、最高気温は24℃~26℃となっており、一日の平均気温が20℃となった。
サニーレタスは、平均気温が20℃頃にならないと、色素成分の“アントシアン”が分解されず、
赤発色しないそうだ!!!
知識はあっても、自分の目で実際に確かめないと、こう言うのって中々納得できないでしょっ!
赤くならない理由は、他にも二つあるからね。
潅水過多と窒素過多・・・、そして今回の気温の問題。
答えがわかってしまえば、“ふ~ん”ってなるけど、それまでは、その答えを見つける為にあれやこれやと考えたりするもんだしね(#^.^#)
今回の場合、うちのサニーレタスがなぜ赤くならなかったのか???は、、、、、
ズバリ!・・・気温が高かったからでしょう(丸尾君風)
4日前に記事にした時の写真と見比べると、色の違いがはっきりわかります!!!
左側の写真が4日前、、、、、 右側の写真が本日撮影のモノです、、、、、
・・・こうして、一つの疑問が解消された。
やっぱこう言う一つ一つの小ちゃな事が、栽培のおもしろさにつながるんだなぁ・・・コレがまた(^^♪
今夏のメイン栽培でもあった、“メロン”!
こいつは、こう言う小ちゃな疑問や問題が他の野菜以上に細かくたくさんあってね、それを一つ一つ検証して工夫して解決して行く事によって、より質の高い果実が作れる事につながるんだ



メロン初栽培で、菜園歴1年半のオレが、何の設備も無い宅庭でも糖度15度以上のメロンが収穫できたのは、それらを積み重ねたからなんだなぁ・・・



マジ野菜栽培は奥ふけ~な~(>_<)
あっ!テレビ見てくれた???
2013年10月13日
さにーれたす“初収穫!(^^)!”
9月16日(月)に苗を定植したサニーレタス!
本日は、定植日より28日目です。
本当は、収穫まであと1週間ぐらいなんだが、昨日、待ちきれなくて食ってしまった^_^;

、、、、、っと言うより、この数日の強風にあおられ、前回記事にした“ツリー”状態で、
草丈36cmもある苗が、“バタッ!!!”って倒れてしまったんだなこれが・・・


ほんで、起こしても起こしても“バタッ!”って倒れるクセがついてしまって、倒れた衝撃で、ついには隣に植えてあるキャベツの小葉を折ってしまったのよ~(-_-;)
こりゃイカンわ!って事で、完全に倒れてしまった苗は、もう抜くことにしたのである。
残りの倒れかけの苗には、短い支柱を添え木代わりにして、順番に食う事にした。。。
収穫の仕方なんだが、地際部分をハサミなんかで切るのがベターなやり方らしいが、オレは根の張り具合が知りたかったので、ゆっくり“ズボッ”と苗ごと引っこ抜きました。
マルチに穴の開いてる部分が、抜いたヶ所です(#^.^#)


混植しているキャベツの根が傷んでしまわないかと若干心配だったが、たぶん大丈夫でしょう
それよりも、根を残しておいた方が、キャベツとの生長の相乗効果が期待できるコンパニオンプランツとしての役割を、果たせたかも知れませんね(>_<)
今回3苗抜きましたが、根の状態もある程度わかりましたので、次回からは地際部分をチョキンとして収穫してみます!!!
1苗は近所のおばちゃんにあげて、残り2苗はうちでバーベキューをやったので、そん時に肉を巻いて食いました


今回初栽培のサニーレタスでしたが、やっぱこの野菜は、先日の記事に書いた通り、、、、、
家庭菜園レベルの栽培なら、ノーリスク・ハイリターンな作物です。
栽培期間も短く、とっても作りやすくて、まず赤字になる事はありませんね!(^^)!
次回は、結球タイプの玉レタスを種から栽培してみる事にします。
苗からだと、簡単すぎて栽培の面白味は全くありませんので・・・。
本日は、定植日より28日目です。
本当は、収穫まであと1週間ぐらいなんだが、昨日、待ちきれなくて食ってしまった^_^;
、、、、、っと言うより、この数日の強風にあおられ、前回記事にした“ツリー”状態で、
草丈36cmもある苗が、“バタッ!!!”って倒れてしまったんだなこれが・・・



ほんで、起こしても起こしても“バタッ!”って倒れるクセがついてしまって、倒れた衝撃で、ついには隣に植えてあるキャベツの小葉を折ってしまったのよ~(-_-;)
こりゃイカンわ!って事で、完全に倒れてしまった苗は、もう抜くことにしたのである。
残りの倒れかけの苗には、短い支柱を添え木代わりにして、順番に食う事にした。。。
収穫の仕方なんだが、地際部分をハサミなんかで切るのがベターなやり方らしいが、オレは根の張り具合が知りたかったので、ゆっくり“ズボッ”と苗ごと引っこ抜きました。
マルチに穴の開いてる部分が、抜いたヶ所です(#^.^#)
混植しているキャベツの根が傷んでしまわないかと若干心配だったが、たぶん大丈夫でしょう

それよりも、根を残しておいた方が、キャベツとの生長の相乗効果が期待できるコンパニオンプランツとしての役割を、果たせたかも知れませんね(>_<)
今回3苗抜きましたが、根の状態もある程度わかりましたので、次回からは地際部分をチョキンとして収穫してみます!!!
1苗は近所のおばちゃんにあげて、残り2苗はうちでバーベキューをやったので、そん時に肉を巻いて食いました



今回初栽培のサニーレタスでしたが、やっぱこの野菜は、先日の記事に書いた通り、、、、、
家庭菜園レベルの栽培なら、ノーリスク・ハイリターンな作物です。
栽培期間も短く、とっても作りやすくて、まず赤字になる事はありませんね!(^^)!
次回は、結球タイプの玉レタスを種から栽培してみる事にします。
苗からだと、簡単すぎて栽培の面白味は全くありませんので・・・。
2013年10月12日
“ほうれん草”のようす2
10月1日(火)に播種した“ほうれん草”


播種当日を1日目とすると、、、、、



順調、順調・・・(#^.^#)
そろそろ双葉も出揃い始めたし、1回目の間引きでもしよっかね~





播種当日を1日目とすると、、、、、
5日目で“発芽”し始め、12日目の本日、こんなに生長しました(*^^)v

完璧!!!美し過ぎる発芽に、感動






順調、順調・・・(#^.^#)
そろそろ双葉も出揃い始めたし、1回目の間引きでもしよっかね~



2013年10月12日
“にんじん”のようす2
9月30日(月)に播種し、5日後の10月5日(土)に発芽し始めた“にんじん”


播種日当日を1日目とすると、本日は播種から13日目になります。
前回の記事からちょうど1週間経ちますが、今日は多くは語りません
発芽させるのが比較的難しい野菜とされている人参ですが、
絵に描いたような『完璧な発芽!!!』に成功しました






全部で11穴、各5粒の点蒔きで播種しました。
双葉が見え始めたので、そろそろ1回目の間引きかな???

にんじんは、間引きを少し遅らせた方が良いとの情報もあるので、じっくり行きたいと思います。
栽培期間も長いんで、収穫は年明けになりそうです。
のんびりゆっくりいきましょう





播種日当日を1日目とすると、本日は播種から13日目になります。
前回の記事からちょうど1週間経ちますが、今日は多くは語りません

発芽させるのが比較的難しい野菜とされている人参ですが、
絵に描いたような『完璧な発芽!!!』に成功しました



全部で11穴、各5粒の点蒔きで播種しました。
双葉が見え始めたので、そろそろ1回目の間引きかな???

にんじんは、間引きを少し遅らせた方が良いとの情報もあるので、じっくり行きたいと思います。
栽培期間も長いんで、収穫は年明けになりそうです。
のんびりゆっくりいきましょう



2013年10月12日
だいこんのようす3“間引き2回目”
9月27日(金)に播種した短大根『三太郎』


本日は、播種から16日目です。
4枚目の本葉がチョロッと育ってきたので、2回目の“間引き”を行いました。
≪間引き前のようす≫、、、、、(before)




どうです???大きくなったでしょ(#^.^#)
防虫ネットのおかげで、害虫被害は全くありません。
湿害にも細心の注意を払っているので、病気は全く皆無で健康苗そのものです(*^^)v
この2回目の間引きで、1穴2苗に絞るそうな
間引きのタイミングについては、本葉2~3枚の頃とか、本葉3~4枚になったらとか、1回目の間引きから2週間後とか、色んなやり方があるみたいなので、オレは自分の苗の状態から判断し、自分流儀のタイミングで行いました。
そんなシビアでもあるめぇ~し、これでイイのだ~


≪間引き後のようす≫、、、、、(after)


間引き前は込み合っていましたが、これでさっぱりしましたね
そして間引時に、1穴3gの化成肥料を追肥しました。
さて、全部で10鉢による大根栽培ですが、その栽培位置は、隣家との垣根であるブロック塀に近い事もあり、宅庭と言う圃場の中で最も日照条件がよろしくない場所であります(-_-)
一度雨が降ると、中々地面が乾きません。
シイタケ栽培なら良いかも???ですが、乾燥を好む野菜には適さない圃場です。
そんな栽培場所なので、鉢を置く、ほんのちょっとの位置の差で苗の生長にも差が出ます。
下の写真は、そんな苗が徒長したモノです。上の写真の苗と比較すると一目瞭然ですね




わかりやすいように、定植位置の全体を撮影してみました。
太陽の位置により若干の日当たりは変わりますが、ほぼ1日こんな感じですね。


左の写真は真正面からの撮影です。
手前側の白い鉢の苗には日が当たっていますが、奥のブロック塀寄りの苗には日が当たっていません。
以前記事にも書きましたが、少しでも苗に光を当てたいので、反射光を利用するため銀シートを
ブロック塀に貼り付けています。
右側の写真は、東側から撮影しています。
白い鉢の方には光があたっていますが、ブロック塀寄りの緑色の鉢には、全く光が当たっていない事がよくわかります。
いずれも正午頃に撮影していますが、朝日はもちろん、午前中の太陽光はほとんど当たりません。
日が沈むにつれて西日の当たりは若干良くなりますが、やはり光合成が活発に行われる午前中の太陽の恵みが欲しいですね


・・・・・さて、次回は3回目の間引きとなり、いよいよ最終的な苗の選択をします。
本葉5~6枚頃に作業を行うそうですが、あとどのぐらいの日数なのかはわかりません。
苗をじっくり観察して、ここだっ ・・・っと言うタイミングで行いたいと思います。
・・・っと言うタイミングで行いたいと思います。
-----------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・播種から10日目
2回目の間引き・・・播種から16日目(1回目より6日後)
3回目の間引き・・・???
-----------------------------------------------------------------------
あと、余談ですが、、、、、
完全無農薬栽培のため、今回の間引いた間引き菜は、“おひたし”にして食しました(^^♪
量はほんのちょこっとでしたが、中々美味でした





本日は、播種から16日目です。
4枚目の本葉がチョロッと育ってきたので、2回目の“間引き”を行いました。
≪間引き前のようす≫、、、、、(before)
どうです???大きくなったでしょ(#^.^#)
防虫ネットのおかげで、害虫被害は全くありません。
湿害にも細心の注意を払っているので、病気は全く皆無で健康苗そのものです(*^^)v
この2回目の間引きで、1穴2苗に絞るそうな

間引きのタイミングについては、本葉2~3枚の頃とか、本葉3~4枚になったらとか、1回目の間引きから2週間後とか、色んなやり方があるみたいなので、オレは自分の苗の状態から判断し、自分流儀のタイミングで行いました。
そんなシビアでもあるめぇ~し、これでイイのだ~



≪間引き後のようす≫、、、、、(after)
間引き前は込み合っていましたが、これでさっぱりしましたね

そして間引時に、1穴3gの化成肥料を追肥しました。
さて、全部で10鉢による大根栽培ですが、その栽培位置は、隣家との垣根であるブロック塀に近い事もあり、宅庭と言う圃場の中で最も日照条件がよろしくない場所であります(-_-)
一度雨が降ると、中々地面が乾きません。
シイタケ栽培なら良いかも???ですが、乾燥を好む野菜には適さない圃場です。
そんな栽培場所なので、鉢を置く、ほんのちょっとの位置の差で苗の生長にも差が出ます。
下の写真は、そんな苗が徒長したモノです。上の写真の苗と比較すると一目瞭然ですね



わかりやすいように、定植位置の全体を撮影してみました。
太陽の位置により若干の日当たりは変わりますが、ほぼ1日こんな感じですね。
左の写真は真正面からの撮影です。
手前側の白い鉢の苗には日が当たっていますが、奥のブロック塀寄りの苗には日が当たっていません。
以前記事にも書きましたが、少しでも苗に光を当てたいので、反射光を利用するため銀シートを
ブロック塀に貼り付けています。
右側の写真は、東側から撮影しています。
白い鉢の方には光があたっていますが、ブロック塀寄りの緑色の鉢には、全く光が当たっていない事がよくわかります。
いずれも正午頃に撮影していますが、朝日はもちろん、午前中の太陽光はほとんど当たりません。
日が沈むにつれて西日の当たりは若干良くなりますが、やはり光合成が活発に行われる午前中の太陽の恵みが欲しいですね



・・・・・さて、次回は3回目の間引きとなり、いよいよ最終的な苗の選択をします。
本葉5~6枚頃に作業を行うそうですが、あとどのぐらいの日数なのかはわかりません。
苗をじっくり観察して、ここだっ
 ・・・っと言うタイミングで行いたいと思います。
・・・っと言うタイミングで行いたいと思います。-----------------------------------------------------------------------
※今までの作業経過※
1回目の間引き・・・播種から10日目
2回目の間引き・・・播種から16日目(1回目より6日後)
3回目の間引き・・・???
-----------------------------------------------------------------------
あと、余談ですが、、、、、
完全無農薬栽培のため、今回の間引いた間引き菜は、“おひたし”にして食しました(^^♪
量はほんのちょこっとでしたが、中々美味でした



2013年10月10日
“きゃべつ”のようす1
サニーレタスと同じく、9月16日(月)に苗を定植したキャベツ!
キャベツは2品種13苗を、プランターで栽培している。
一品種は、『みさき』、、、はっきり言って、こいつはむちゃくちゃウマイ


昨年、栽培に成功した筍型の品種で、想像を絶する“うま味”のあるキャベツだ。
たぶん、この辺のスーパーでは売っていません・・・。栽培した人だけが味わえるキャベツです



もう一品種は、キャベツの定番『あまだま』。
昨年は、一応成功した部類には入るものの、何せ初栽培の無知で、深型とは言え10号鉢なんかで栽培したモンだから、超小型に仕上がりました。
げんこつ2個分ぐらいの大きさだったでしょうか???まあ、それでもちゃんと結球したんですがね^_^;
20L程度と言う、あまりにも少な過ぎる土量のため、小型化してしまったのを反省し、、、、、
今回は1玉50Lの土量だ



・・・とは言え、とりあえず、コンパニオンプランツのサニーレタスと混植しているので、土を分け合う密植状態だが、不思議な事に、キャベツ1玉単体で栽培するよりも、サニーレタスと密混植した方が、なぜかキャベツが大型化すると言う、農業系雑誌に掲載された実験結果もある。
混植する事によって防害虫にもなるそうなので、にわかには信じ難いが、オレも実験中である。

サニーレタスの栽培期間とキャベツの栽培期間は当然異なるので、最後まで混植と言う訳にはいかないが、キャベツの幼苗期~の防害虫に効果を発揮する意なので、サニーレタスが30~40日間の栽培期間であるため、キャベツの幼苗期~伸長期とほぼ一致し、なるほど!!!
“理に叶っている”と思ったオレ^m^ただ時期が被っていると言うだけなんだがね・・・。
しかしながら、店側は1苗でも多くの種や苗を売りさばきたいはずなんで、ダマされてんのかなぁ~とも思う・・・。
やってみるだけやってみようと言うのが今年のオレの栽培方法だし、まあ、いっかっ


キャベツは2品種13苗を、プランターで栽培している。
一品種は、『みさき』、、、はっきり言って、こいつはむちゃくちゃウマイ



昨年、栽培に成功した筍型の品種で、想像を絶する“うま味”のあるキャベツだ。
たぶん、この辺のスーパーでは売っていません・・・。栽培した人だけが味わえるキャベツです



もう一品種は、キャベツの定番『あまだま』。
昨年は、一応成功した部類には入るものの、何せ初栽培の無知で、深型とは言え10号鉢なんかで栽培したモンだから、超小型に仕上がりました。
げんこつ2個分ぐらいの大きさだったでしょうか???まあ、それでもちゃんと結球したんですがね^_^;
20L程度と言う、あまりにも少な過ぎる土量のため、小型化してしまったのを反省し、、、、、
今回は1玉50Lの土量だ



・・・とは言え、とりあえず、コンパニオンプランツのサニーレタスと混植しているので、土を分け合う密植状態だが、不思議な事に、キャベツ1玉単体で栽培するよりも、サニーレタスと密混植した方が、なぜかキャベツが大型化すると言う、農業系雑誌に掲載された実験結果もある。
混植する事によって防害虫にもなるそうなので、にわかには信じ難いが、オレも実験中である。
サニーレタスの栽培期間とキャベツの栽培期間は当然異なるので、最後まで混植と言う訳にはいかないが、キャベツの幼苗期~の防害虫に効果を発揮する意なので、サニーレタスが30~40日間の栽培期間であるため、キャベツの幼苗期~伸長期とほぼ一致し、なるほど!!!
“理に叶っている”と思ったオレ^m^ただ時期が被っていると言うだけなんだがね・・・。
しかしながら、店側は1苗でも多くの種や苗を売りさばきたいはずなんで、ダマされてんのかなぁ~とも思う・・・。
やってみるだけやってみようと言うのが今年のオレの栽培方法だし、まあ、いっかっ



2013年10月10日
“さにーれたす”のようす1
9月16日(月)に苗を定植したサニーレタス!
“レッドファイヤー”と言う品種名である。
・・・ウ~ム(・_・;)・・・!?
“炎のような赤”みたいな商品名なのに、なぜかうちのはグリーンだ!!
新鮮さがただよう、ツヤッツヤのきれいな緑色なのだが、レッドでは無い・・・。何故なんだ???

リーフレタス、と、サニーレタス・・・。
どちらも非結球タイプのレタスである事は知っているが、その違いは何なんだ???
疑問に思い調べた。
リーフレタスとサニーレタスの違いは、すぐわかった(^_^)v
日本では、非結球レタスを総称して『リーフレタス』と言い、その中で、赤色種を『サニーレタス』、緑色種を『グリーンリーフ』と言うらしい・・・。知ってましたか???
オレは初めて知った・・・なるほど!


ちなみに『サニーレタス』は、日本人が名付けた造語のようでして、、、、、
英語圏で買い物する時に「サニーレタスくれっ!」と言っても、「???」・・・っとなるそうなので、
英語圏では「red leaf lettuce(レッドリーフレタス)くれっ!」と注文しましょうwwwww
さらに、このサニーレタス、、、、、愛知県の朝倉さんが研究開発をして、世界で初めて作ったそうですよ!
調べてみると、野菜の雑学も意外におもろいですな~^m^

さて、肝心な栽培についてなのだが、、、、、
赤色種なのになぜ緑色なのか???って理由なんだが、ちょいと調べるのに手間取っちまった^_^;
検索しても、素人のブログやら素人回答のQ&Aばっかしで、プロのそれが中々出てこん!
-------------------------------------------------------------------------------------------
以前にも書いたが、野菜栽培において、オレは素人情報は全く信じていない。
そんなモン全くあてになんね~からな


このブログにも『OO栽培の仕方』、『OO害虫の対処法』などの語句でググってくる方が結構いるんですが、
“栽培成功の秘訣”は、プロの話しを直接聞く事!!!
これ、素人野菜栽培の鉄則アルネ!!!
プロの生産者、種苗メーカー(窓口担当は無知だから☓)の専門の担当者、なんかが良いね!
農業試験場はマニアック過ぎかもだけど、最新の栽培技術や、流行している病気や害虫、その対処法なんかが学べるぞ!
体験型ワークショップもあるし、生産者とはまた違うプロの研究機関だから、情報収集の一つとしてオレは活用している。
来月に、県の総合農業試験場でイベントがあるんで行きたかったのだが、仕事で行けね~(T_T)
-------------------------------------------------------------------------------------------
・・・、探したらありました。とある種苗店のブログに!(^^)!
なぜ赤くならないのか???簡単にまとめると、、、、、
1.気温が高いので
2.潅水過多
3.窒素過多
、、、、、っとなり、赤くするには前述と逆の事をすれば良い!
1.低温期に栽培
2.乾燥気味に栽培
3.窒素分を少なく栽培
、、、、、っとなる!なるほど・・・(>_<)
オレの場合、まだ気温が高いのに(これはしょうが無い)、毎日潅水して、あまり必要のない追肥(高度液肥=N:15・P:6・K:6)を指定濃度より高濃度で施肥してしまったので、おかげでみどり~の葉になりました(;一_一)
そもそも、キャベツのコンパニオンプランツとして栽培しているで、以前記事にもしたが、赤発色させないと害虫被害の軽減化が図れ無いのよねェ~


それとさぁ、非結球タイプはわかんだけど、出来上がりの苗の形が想像とまるで違うんだよね~f^_^;
もうちょっと、、、、、こう、、、全体が丸みをおびて“フワフワッ”っとした感じをイメージしてたんだが、これではどうにも程遠いね



地際から上へ“ヌッ”と直立した幹に、枝葉が茂っている感じで、なんか観葉植物的な“ツリー(木)”みたい・・・。密植の影響もあるかもね。それとも、こういうタイプの品種なんかな


栽培自体は、苗からなら“超easy”ですね。
小学校低学年でも栽培可能です。
気軽に栽培できるにしては、意外にハイリターンな作物かと思いますので、こりゃ初心者におすすめですな


うちは、あと1週間も経てば収穫なので、どんな味に仕上がっているのか、楽しみだ


“レッドファイヤー”と言う品種名である。
・・・ウ~ム(・_・;)・・・!?
“炎のような赤”みたいな商品名なのに、なぜかうちのはグリーンだ!!
新鮮さがただよう、ツヤッツヤのきれいな緑色なのだが、レッドでは無い・・・。何故なんだ???
リーフレタス、と、サニーレタス・・・。
どちらも非結球タイプのレタスである事は知っているが、その違いは何なんだ???
疑問に思い調べた。
リーフレタスとサニーレタスの違いは、すぐわかった(^_^)v
日本では、非結球レタスを総称して『リーフレタス』と言い、その中で、赤色種を『サニーレタス』、緑色種を『グリーンリーフ』と言うらしい・・・。知ってましたか???
オレは初めて知った・・・なるほど!



ちなみに『サニーレタス』は、日本人が名付けた造語のようでして、、、、、
英語圏で買い物する時に「サニーレタスくれっ!」と言っても、「???」・・・っとなるそうなので、
英語圏では「red leaf lettuce(レッドリーフレタス)くれっ!」と注文しましょうwwwww
さらに、このサニーレタス、、、、、愛知県の朝倉さんが研究開発をして、世界で初めて作ったそうですよ!
調べてみると、野菜の雑学も意外におもろいですな~^m^
さて、肝心な栽培についてなのだが、、、、、
赤色種なのになぜ緑色なのか???って理由なんだが、ちょいと調べるのに手間取っちまった^_^;
検索しても、素人のブログやら素人回答のQ&Aばっかしで、プロのそれが中々出てこん!
-------------------------------------------------------------------------------------------
以前にも書いたが、野菜栽培において、オレは素人情報は全く信じていない。
そんなモン全くあてになんね~からな



このブログにも『OO栽培の仕方』、『OO害虫の対処法』などの語句でググってくる方が結構いるんですが、
“栽培成功の秘訣”は、プロの話しを直接聞く事!!!
これ、素人野菜栽培の鉄則アルネ!!!
プロの生産者、種苗メーカー(窓口担当は無知だから☓)の専門の担当者、なんかが良いね!
農業試験場はマニアック過ぎかもだけど、最新の栽培技術や、流行している病気や害虫、その対処法なんかが学べるぞ!
体験型ワークショップもあるし、生産者とはまた違うプロの研究機関だから、情報収集の一つとしてオレは活用している。
来月に、県の総合農業試験場でイベントがあるんで行きたかったのだが、仕事で行けね~(T_T)
-------------------------------------------------------------------------------------------
・・・、探したらありました。とある種苗店のブログに!(^^)!
なぜ赤くならないのか???簡単にまとめると、、、、、
1.気温が高いので
2.潅水過多
3.窒素過多
、、、、、っとなり、赤くするには前述と逆の事をすれば良い!
1.低温期に栽培
2.乾燥気味に栽培
3.窒素分を少なく栽培
、、、、、っとなる!なるほど・・・(>_<)
オレの場合、まだ気温が高いのに(これはしょうが無い)、毎日潅水して、あまり必要のない追肥(高度液肥=N:15・P:6・K:6)を指定濃度より高濃度で施肥してしまったので、おかげでみどり~の葉になりました(;一_一)
そもそも、キャベツのコンパニオンプランツとして栽培しているで、以前記事にもしたが、赤発色させないと害虫被害の軽減化が図れ無いのよねェ~



それとさぁ、非結球タイプはわかんだけど、出来上がりの苗の形が想像とまるで違うんだよね~f^_^;
もうちょっと、、、、、こう、、、全体が丸みをおびて“フワフワッ”っとした感じをイメージしてたんだが、これではどうにも程遠いね



地際から上へ“ヌッ”と直立した幹に、枝葉が茂っている感じで、なんか観葉植物的な“ツリー(木)”みたい・・・。密植の影響もあるかもね。それとも、こういうタイプの品種なんかな



栽培自体は、苗からなら“超easy”ですね。
小学校低学年でも栽培可能です。
気軽に栽培できるにしては、意外にハイリターンな作物かと思いますので、こりゃ初心者におすすめですな



うちは、あと1週間も経てば収穫なので、どんな味に仕上がっているのか、楽しみだ